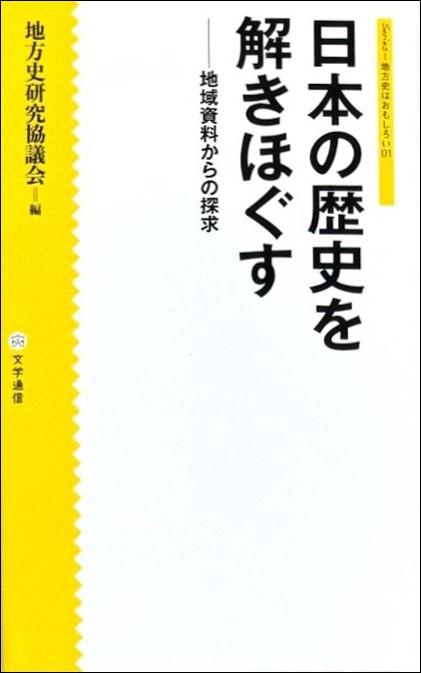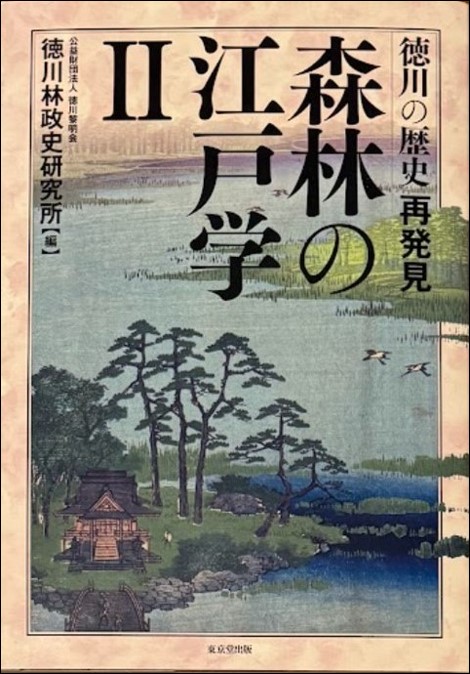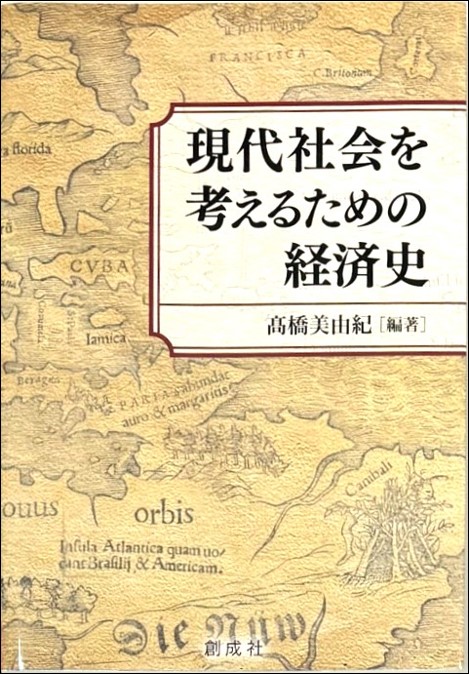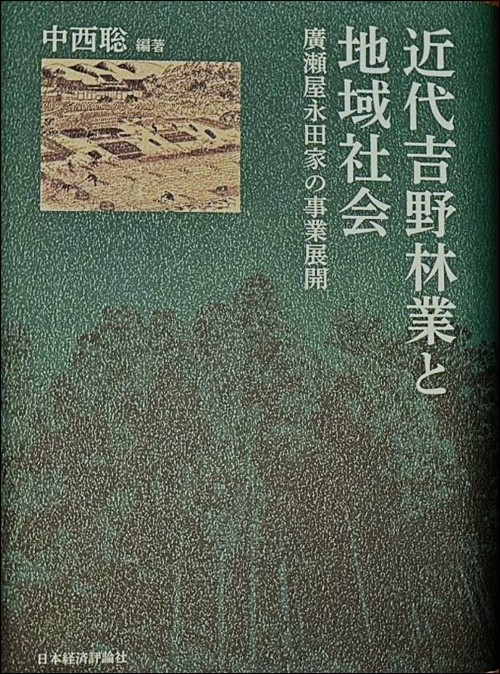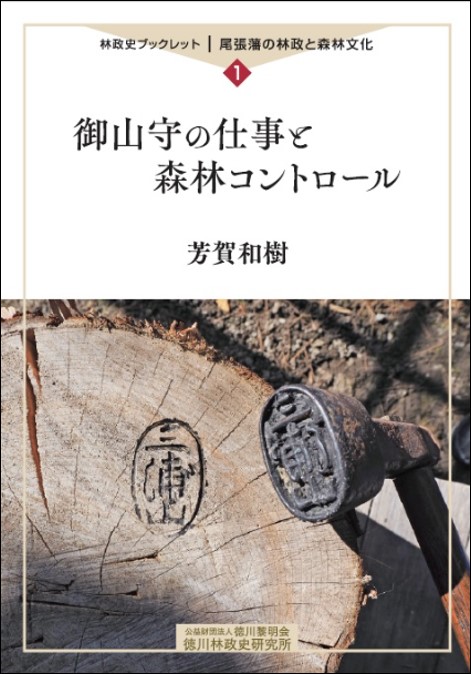ゼミテーマ
- 「人間と人間」「人間と自然」の関係の変容を長期的視野から考える
担当教員
- 芳賀和樹
ゼミ概要
この研究会では、「人間と人間」の関係、「人間と自然」の関係の変容を長期的視野から考えます。具体的なテーマは、ゼミのなかで相談しながら決定します。
―これまでにとりあげた具体的なテーマ―
東京湾、富士山、温泉、病と医療、自然観、特産物と食、鉄道、宿場、寺社、祭り、着物、文化、結婚式、教育、出版、ごみ処理と3R、など
ゼミの進め方
①入門書や歴史資料を読み解くことで、基本的な知識や研究手法を習得するとともに、各自の関心を深める。
②各自の関心にそくして「問い」を立て、文献調査やフィールドワークなどを行い、「答え」を共有・議論する。
③以上から、具体的な事例に基づいて、「人間と人間」の関係、「人間と自然」の関係の変容を長期的視野から考える。
―「問い」の例―
・農山村における家族や生業、暮らしのあり方は、どのように変容してきたのだろうか?
・東京湾の開発、鉄道の敷設は、どのように進められ、近代以降の日本の展開にどのような役割を担ったのだろうか?
・地域の名物や観光地(景勝地や寺社など)は、どのように形成されてきたのだろうか?
・食糧や飲料水といった生活必需品は、どのように確保されてきたのだろうか?
・洪水や土砂災害のリスクは、どのように軽減されてきたのだろうか?
学生の皆さんへのメッセージ
教員の主な研究分野は「日本史」「環境史」です。「歴史は暗記系の学問」というイメージがあるかもしれませんが、歴史学の醍醐味は、データを時系列順に整理し、人間がこれまでどのように生きてきたのか、どのように生きていくのかを考えるところにあると思います。未来を考えるとき、人間は検討材料として過去を参照します。長期的視野から過去・現在・未来を見通そうとするのが歴史学だといえるでしょう。
たとえば、歴史学の現代的意義として、次の2つをあげることができます。
①地域の個性の「再発見」→それぞれの魅力を活かした地域活性化に寄与
②在来知・伝統知(歴史的に蓄積されてきた知識や技術)の「再発見」→地域の資源の利用・管理、防災・減災のためのヒントの獲得
本研究会では、時間として主に江戸時代~現在を(江戸時代を含まなければならないということではありません)、空間として日本をとりあげますが、さらに古い時代や日欧比較などに関心がある場合には相談してください。
書籍の紹介
・中西聡編『近代吉野林業と地域社会―廣瀬屋永田家の事業展開―』日本経済評論社、2024年(第3章)
・高橋美由紀編『現代社会を考えるための経済史』創成社、2023年(第10章)
・芳賀和樹『御山守の仕事と森林コントロール』徳川林政史研究所、2020年
・地方史研究協議会編『日本の歴史を解きほぐす―地域資料からの探求―』文学通信、2020年(第6章)
・徳川林政史研究所編『徳川の歴史再発見 森林の江戸学』Ⅱ、東京堂出版 2015年(総説など)