PickUP
【法政の研究ブランドvol.32】会計学の本質をベースに「健康経営」に着目した会計モデルの構築に取り組む(人間環境学部人間環境学科 金藤 正直 教授)
- 2025年03月05日
- 教員
日本の大多数を占める中小企業の持続可能性を会計面から考える

現在、法政大学大学院特定課題研究所の一つ、「中小企業サステナビリティ経営研究所」の研究代表者として、「中小企業の持続可能性を高める経営や会計に関する研究・調査」を行うとともに、「企業の業績向上を実現させる健康経営システムに資する会計モデルの研究」というテーマで科研費助成を受けた研究にも取り組んでいます。
「中小企業サステナビリティ経営研究所」ですが、2023年度秋学期に開講した人間環境学部「人間環境セミナー」というオムニバス形式の授業が発足の契機となりました。中小企業のサステナビリティに関するテーマを扱う内容だったのですが、土曜日にもかかわらず多くの履修者が集まり、関心の高さを実感しました。そのため、講義を担当してくださった実際に課題に取り組む経営者の方々と、日本の企業のほとんどを占める中小企業の課題について考える意義を確認し合い、設立に至りました。
本研究所は、文系の研究者の割合が多いのですが、理系やデザイン系の分野の研究者も参加しています。デザイン経営やデザイン思考という言葉がありますが、目の前の課題を最終的にどのようにイメージしていくかという、デザイン的な視点は、私たち研究者がどこへ向かっているのかを「見える化」してくれるという意味で、非常に重要です。私は経営学の中でも会計学の研究がメインのため、これまで行ってきた古典的な文献調査に基づく会計学の本質をベースとしています。そのうえで、これからの中小企業が環境経営、サステナブル経営と言われる中で、どのような会計の仕組みを構築すればいいのかという視点で研究に参加しています。
「企業の業績向上を実現させる健康経営システムに資する会計モデルの研究」についてですが、近年企業において「健康経営」という言葉が聞かれるようになってきました。これは簡単に言えば、職場で働く従業員の健康を保つことを経営の柱の一つにするということに他なりません。
「健康経営」が企業の社会的責任であり持続可能性を高める
企業を構成しているのは「株主」という見方もあるでしょう。しかし、実際に職場で働く従業員が健康を害してしまえば、企業は立ち行かなくなります。従業員が急死したり入院したりすれば、業務がストップしてしまい業績にも大きく影響します。それだけではなく、労災による多額の損失を生むというリスクにもつながりかねません。そうした事態を未然に防ぐため、また、日々の労働環境を見直して、従業員の心身を含めた健康に配慮した健康経営こそが、企業の社会的責任であり、持続可能性を高めてサステナブルな企業を展開するうえで、最も大切なことではないかと考えています。
例えば、ある小売業をメインとする企業では、産業医とともに健康経営やサステナブルに力を入れていますが、企業が従業員のウェルビーイングに配慮した取り組みを継続することで、従業員の快適度や幸福感が増し、営業利益にも貢献するということを、感覚的なものではなく、ある程度数値的に可視化したそうです。このように、健康経営の目的は、従業員の心と体の健康を向上させることだけではなく、こうした取り組みの先に業績アップというゴールに結び付かなければなりません。ここに私の専門である会計学という視点が貢献できると考えています。会計学と聞くと一般的には、B/S(貸借対照表)、P/L(損益計算書)、C/F(キャッシュフロー計算書)を思い浮かべるのではないでしょうか。会計学が扱う分野は実はとても幅広く、数値の情報開示方法やサステナブルな経営への応用を検討するのも私たちの研究ですし、これまで計算されていなかった非財務的な数値にも着目します。
比較的新しい経営指標である健康経営には、明確な指標がないことから、私はバランス・スコアカード(BSC)を用いた健康経営評価モデルの開発に取り組んでいます。BSCとは、財務的な数値だけではなく、非財務的な数値も用いて、①財務、②顧客、③業務プロセス、④人材と変革、という4つの視点から業績を測定・評価し、企業が策定したビジョンや戦略の達成を促すシステムです。
企業における健康経営が業績に結び付くストーリーをしっかりと組み立て、従業員の健康が、実際どの程度業績に関与するのか、具体的にどのくらい業績向上につながるのかといったところまで検証し、新たな会計モデルを構築できればと思っています。
「健康経営」に資する会計モデル構築の難しさ
一般的な会計モデルであれば、企業の通常の経営を見ればよいのですが、健康経営に着目してみると、例えば業績が落ちていた際、その理由としてキーパーソンとなっている従業員の健康上の問題やストレスを抱えているのではないか、周りの人とうまくいっていないのではないか。さらにそれが個人的な問題なのか、働く環境によるものなのか、と考えます。
では実際にどのように健康経営を取り入れていくのかを考えてみると、企業によってはそれまでの会社の制度や環境を全面的に刷新するというところもあるのですが、私はむしろ、部分的に健康経営を導入して、その有効性を明らかにしていくことがより好ましいと考えています。それによってどのような施策が実際の業績に影響するのかを検証でき、汎用的な健康経営における会計モデルの構築に貢献できるからです。また、従業員にとっても、制度や環境がガラッと変わることによる抵抗や恐怖心を感じずに済むというメリットもあります。
モデル化と聞くと、どの会社でも通用するような共通した仕組みと考えてしまうかもしれませんが、従業員という人を対象としているわけですし、その人が働く環境も周りにいる人も異なるわけですから、症状としては同じでもそこに至る原因は異なります。そのため、私たち研究者からすると、共通のモデルをそのまま取り入れましょうということにはなりません。そのため、とても難しいことではありますが、企業特性やそこにいる人のパーソナリティを十分考慮した上で、それぞれの課題を解決できるような健康経営の在り方を模索していかなければならないのです。
健康経営を導入するためには、まず従業員一人一人に自身の健康を意識してもらうところからスタートしなければなりません。そのためにも、働く人の健康度が企業にとってどのような意義を持つのか、ということをまずは伝えることが大切でしょう。
研究の軸である会計学×SDGsという視点で大学・教育にも寄与
私が健康経営に興味をもったのは2010年前後ですが、それ以前から研究の軸は企業会計や会計システムです。ただ、それをベースに環境や地域、農業といった様々な分野に関心を広げてきました。例えば、青森県におけるりんご産業クラスター事業の問題とその改善策については、事業を取り巻く企業、自治体、農家などといった様々なステークホルダーが地域振興の現状を明らかにできる会計システムを構築し、補助金や助成金が実際にうまく運用され、新たな商品の生産・販売によって利益が得られているかという取組状況をリアルに示すことが重要だと考え、研究に携わりました。
法政大学でも研究のバックグラウンドを活かし、カーボンニュートラルの推進など、大学全体の環境やSDGsへの取り組みに積極的に参加しています。また高大連携やゼミなどで、教育へも寄与しています。ゼミでは、「企業や地域の持続的な成長を実現していくためのビジネスデザイン」というテーマのもと、11のプロジェクト(2025年度から12のプロジェクト)を行うチームに分かれ、いずれかに所属して2年生から3年間、自分たちで成果を出し、時には私が所属する学会で発表するなどの場も設けています。また、東京ビックサイトで開催されている環境総合展「エコプロ」にも学生が主体となって出展し、ここで各チームの研究成果を紹介しています。
研究と言うと少々堅苦しく聞こえるかもしれませんが、学生の皆さんはせっかく企業とも連携して、実際に製品を開発するなど実践的な経験をしているわけですから、自分たちがやってきたことを、卒業研究として体現化できるような卒業論文にチャレンジしてほしいですね。
-

環境総合展「エコプロ」への出展の様子(2023年12月)
-

「2023年度自由を生き抜く実践知大賞」において、金藤ゼミのアパレルチーム「残反プロジェクト」が「社会の課題解決賞」を受賞(2023年12月)
-
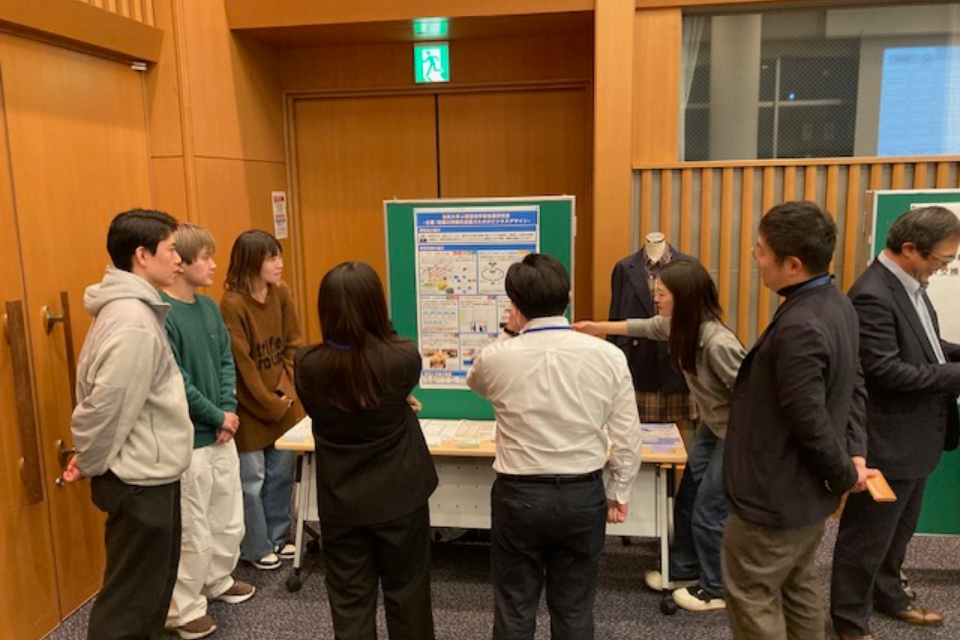
「2024年度第2回法政大学SDGsパートナーズ交流会」でのポスターセッションの様子(2024年12月)
-

2024年度金藤ゼミ合宿時の集合写真
人間環境学部人間環境学科 金藤 正直 教授
2004年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科企業システム専攻博士後期課程修了(博士(経営学))。東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻産学官連携研究員を経て、弘前大学人文学部の専任講師、准教授を歴任。2014年4月より法政大学人間環境学部准教授、2019年4月より現職。研究テーマは、企業や地域の持続的成長を実現するビジネスモデルやマネジメントシステム。2024年には法政大学大学院特定課題研究所「中小企業サステナビリティ経営研究所」を設置し、国内の中小企業に対して「攻め」のサステナビリティ経営の展開方法を検討・提案している。

