社会問題に触れ、自身に芽生えた違和感の根源を見つけ出す
社会的排除や人権問題などに関する文献調査や、関係者への聞き取り調査を通じて、ゼミ生の関心の芽を育み、3年かけて卒業論文へとつなげている別府ゼミ(ジャーナリズム論)。
在日外国人にまつわる諸問題に取り組んでいるのは村木さん。「在日朝鮮人に関する実態を知ろうと、高麗博物館や東京朝鮮第九初級学校などの関連施設を訪問して調査しました。成果発表は終えましたが、まだやり切っていないので、リサーチ力を高めて、さらに理解を深めたいです」と、今後の研究計画を練っています。
ジャーナリズムと教育に関心を寄せる村上さんは、「弱者の声を聞き漏らしたくない」という思いから「LGBTQと家族」「いじめ問題」などに着手。「当事者にお話を聞くなど、背景を把握するための調査を進めながら、実践と理論を身に付けようと努めています。生きづらさを感じる人に手を差し伸べる方法を探し、自分の将来につなげたい」と語ります。
「学生には、自ら問いを立て、内省しながら自分の疑問や違和感の根源は何かを見つけ出してほしい」と語る別府教授。その思いに応えるように、学生らは本ゼミの時間以外も、自発的にサブゼミを実施して考察を深めるなど、精力的に活動を続けています。それらの研究成果は、例年11月に開催される社会学部研究発表会で報告する他、論文集を作成するなど、さまざまな形で集約しています。
2021年度には、太平洋戦争末期にフィリピンで行われた「ルソン島の戦い」を知って心を動かされた学生らが自主的に現地を調査し、その過程を記録したドキュメンタリーフィルム「ルソンの祈り〜順子ちゃんの戦場をたどって」(40分)を企画・制作。映像コンクール『第41回「地方の時代」映像祭』にて市民・学生・自治体部門の優秀賞を受賞するなど、高い評価も得ました。
その作品に感銘を受けたという金崎さんは、クルド人民族問題や刑事事件の加害者の社会復帰など、幅広いテーマに関心を示し、探求しています。「加害者と被害者など、相反する関係性のどちらもがさまざまな困難を抱えています。それならば自分は何を軸とすべきか、学生の間にしっかりと考え抜きたい」と、仲間と語り合い思索を重ねています。
「ゼミの活動を通じて、社会的に問題を抱えている人たちの存在に気付き、調査して実態を知ることで、視野が広がりました」と研究の成果を実感している山本さん。「当人の立場を理解したり、さまざまな視点を持って人を助けられるように努めたい」と、将来を見据えて語ります。
(初出:広報誌『法政』2022年6・7月号)
※今回はオンラインで取材しています。
-

上段左から別府三奈子教授、金崎龍ノ介さん(社会学科4年)、山本誠さん(社会政策科学科4年)、下段左から村木健太さん(メディア社会学科3年)、村上遥香さん(メディア社会学科3年) *全員、社会学部 ※今回はオンラインで取材しています
-

例年、春学期は共通テキストを輪読し、専門的な視野の形成を図っている。2022年度は『<被爆者>になる』(せりか書房、2016年)を題材として議論している
-
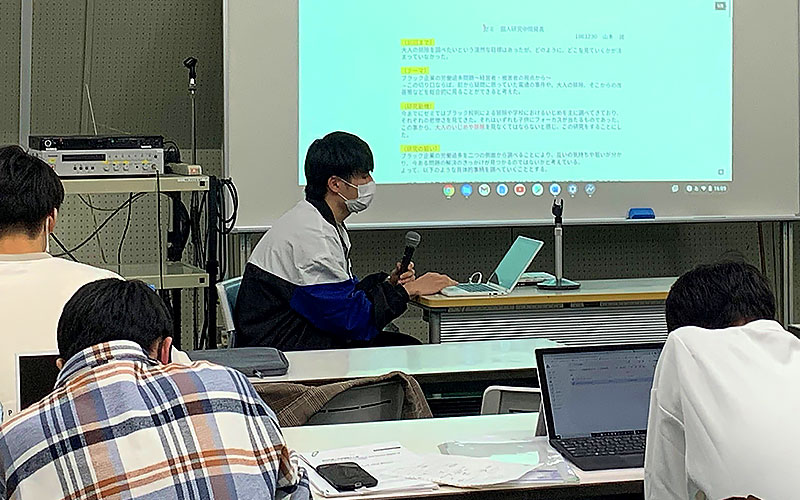
緊急事態宣言が解除された、2021年11月に八王子の大学セミナーハウスで合宿を開催。各自が手掛けている研究を発表し、意見交換を重ねた
-

フィールド調査なども、学生主体で精力的に行っている。写真は、2019年5月に実施した、長崎県佐世保市の釡墓地戦没者慰霊祭での聞き取りの様子

