「法政の研究ブランド」シリーズ
法政大学では、これからの社会・世界のフロントランナーたる、魅力的で刺激的な研究が日々生み出されています。
本シリーズは、そんな法政ブランドの研究ストーリーを、記事や動画でお伝えしていきます。
マクロ経済学は、時代が求める実社会に根ざした学問
GDPや物価、金利、失業率といった指標を用いて、国全体の経済を大きな視点で捉えるマクロ経済学。現在では政策立案の土台ともなる学問ですが、そのルーツは意外と新しく、20世紀のアメリカ、大恐慌の最中に生まれました。従来の経済学では太刀打ちできない未曽有の不況に直面し、新しいアプローチの必要性が高まった末に誕生したのがマクロ経済学だったのです。実社会に根ざした学問として発展し、日本でも戦後復興や財政政策の立案に活用されてきました。
私がマクロ経済学の研究で用いているのが、「DSGE(動学的確率的一般均衡)モデル」です。これはかみ砕くと、「時間軸」「経済ショック」「マーケットの均衡」の3要素を組み込み、経済の変化がもたらす影響を理論的にシミュレーションする手法です。例えば、政府が金利を下げたときに、経済を構成する家計や企業が、どれくらいの時間をかけてどのように行動に移すのかを予測。政策の有効性を検証することができます。
財務省で研究官として勤務していた頃は、このモデルを使って経済政策の効果を検証したり、他国の事例と比較したりしていました。国によってデータや目的が違うため、同じ手法を用いても結果はもちろん異なります。経済モデルをどこまで現実に近づけるべきか、その問いを起点に研究を続けてきました。

「消費と余暇」の視点からよりリアルな政策を
経済を考える中で、私がとりわけ興味を持ったのが「家計」の行動です。消費や貯蓄といった家計の行動は、経済全体の中でも非常に大きな割合を占めます。だからこそ、しっかりと把握しなければ、現実に即した経済モデルはつくれません。そこで注目したのが、「消費と余暇」のバランスです。消費のきっかけは余暇の量にも影響されますよね。時間がたくさんあるから消費しようと思う人もいれば、逆に余暇が取れないからこそ消費で満足度を補おうとする人もいるでしょう。
実際にデータを用いて分析してみたところ、消費の異時点間代替弾力性(IES)――つまり消費者が金利の変化にどれくらい反応するかを示す指標の値が、余暇を加味するかどうかで大きく変わる事実が明らかになりました。しかし従来のマクロ経済モデルでは消費と余暇のバランスという要素が考慮されていないため、政策の効果を過大評価してしまうリスクがあることも見えてきたのです。さらに私の研究では、消費と余暇は代替されるものであり、片方が減ってももう片方が増えれば、同じような満足感を得られるという推計結果が出ました。こうした要素を加味しながら、より現実に即したシミュレーションができるよう研究を進めています。
研究対象は日本国内にとどまりません。財務省時代には50〜60の国や地域を対象に、複数の国の経済がどう影響し合うかを分析できる「NiGEM」という多地域型マクロ計量モデルを使い、コロナ禍の経済回復シナリオのシミュレーションにも携わりました。財政と金融の政策をどう組み合わせるのが最も効果的なのか。政策ミックスをいくつも試しながら、現実的な対策に近づけていく作業は非常に刺激的でした。
世界で通用するスキルとして経済学を探究
私が経済学に興味を持ったきっかけは、父の存在です。幼少期を西ドイツで過ごし、現地法人で経営に携わる父の姿を見て、世界で通用するスキルや知識を身に付けたいという思いが少しずつ芽生えていきました。大学卒業後、一度は就職したのですが、「本場で経済学を学ぶ」という意欲が高まり、アメリカへ留学し、そのまま現地の大学に就職しています。最先端の研究環境に身を置き、経済学の奥深さと面白さに触れました。日本の少子高齢化はアメリカでも常々話題になっており、この課題に自分の研究で向き合いたいと考え、財務省の主任研究官として帰国しました。実務に携わる中で法政大学の恵まれた研究環境を知り、ご縁があって現在に至ります。
法政大学に来てからは東京在住の研究者との接点が非常に増え、学問分野の垣根を越えてさまざまなコラボレーションができています。私のような実務経験を持つ教員が多く、社会人学生や外国人留学生も多く在籍しているため、英語を交えた議論も盛んです。刺激を与え合いながら行う研究は、現実問題に根ざした深い洞察を可能にしていると感じます。日常会話などふとしたきっかけから化学反応が起き、互いのスキルを掛け合わせて新たな展開が生まれる瞬間はとてもエキサイティングです。私の関心も経済学以外の分野に広がっており、マクロ経済学の専門性をベースにしながら、機械学習(コンピュータが自動で学習し、大量のデータからパターンやルールを分析する手法)や社会学との接点も探り始めています。
経済学の魅力は、世界中で通用する知識や法則が数多くあることです。アメリカにおける医療インフレの問題を取り上げた私の論文が、アフリカや中東の国々でも参照されていたと知ったときは、経済学が「世界共通の言語」であると実感しました。
-
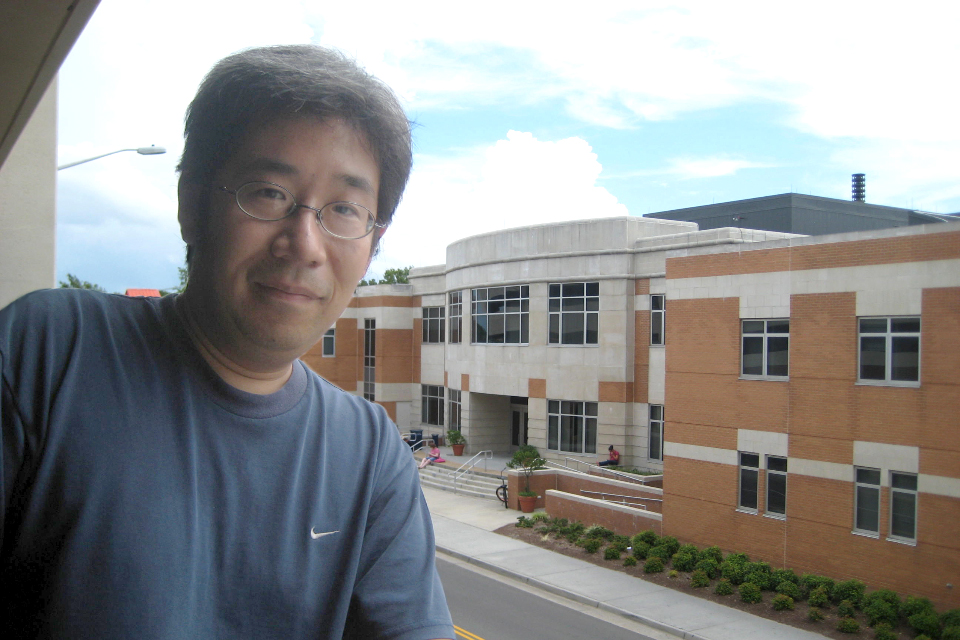
2011年から約7年間、経済学部助教授を務めたオールドドミニオン大学にて
-

財務省勤務時、2019年にチェコで行われたDSGEモデルの研修に参加
社会の変化を敏感に捉え、広い視野で研究に挑む
私の研究はマクロ経済学、計量経済学、医療経済学、労働経済学、財政学と多岐にわたる分野を横断しており、扱うテーマも医療や夫婦の時間配分など実にさまざまです。
今後の日本の財政を考える上で、医療分野は非常に重要なトピック。アメリカ時代に行った、時間と医療費の補完関係についての研究は、今後日本のデータで分析し直したいと思っています。医療や健康は、日々の積み重ねで増やしていく人的資本として捉えることができます。特に健康は年齢を重ねるごとに減ってしまう減価償却型の資本ですから、それをどう維持していくのかが、経済学的な視点では大きなテーマになるでしょう。社会制度や個人の意思決定などさまざまな要素が絡む中で、経済成長と両立させるために何をすべきかと考えると、大変やりがいのある課題だと感じます。
これからは、高齢化が進む日本における消費と労働の関係性についてより詳しく分析していく必要があります。また、最近話題になった「スーパーパワーファミリー」と呼ばれるような消費意欲の高い家計と、消費税増税の中で教育費などのやりくりに苦心する家計との格差問題にも注目しています。国民一人一人が豊かさを実感できる社会を実現するためには、社会の小さな変化を敏感に捉えていくことが欠かせません。アメリカで培ったフットワークの軽い柔軟な研究姿勢と、日本の社会課題への問題意識、両方を大切にしながら政策現場のニーズに応える「実践知」を追い求めていきたいです。
学生に対しては、エビデンスに基づいた政策立案の重要性を伝えています。マクロ経済学は、多くの人々にとって遠い存在かもしれません。しかし、ほんの少しでも身近に感じてもらい、ビジネスに関わる一人一人が共通認識としてマクロ経済学の知識を持つことで、日本の将来設計に参画できる社会を実現したいと考えています。
法制度、働き方、家族のかたち、健康や医療──。今後も社会の変化の兆しを見逃さず、経済学というレンズを通して読み解いていきます。
-

八木橋ゼミでのディベートの様子(2025年6月)
-

八木橋ゼミの学生達と謝恩会にて(2025年3月)
経済学部経済学科 八木橋 毅司 教授
2008年カリフォルニア大学デービス校で経済学博士号取得。卒業後10年間、北米の大学にて研究・教育に従事。財務省財務総合政策研究所で主任研究官として勤務した後、2021年4月より現職。マクロ経済学、国際マクロ経済学、応用計量経済学などを専門分野とし、主な研究テーマはモデルの不確実性及び消費と貯蓄。論文に“Are DSGE Approximating Models Invariant to Shifts in Policy?”(De Gruyter、2010年)、「日本の消費の異時点間代替弾力性についての一考察」(財務省、2020年)、「マクロ経済モデルのフロンティアー海外の活用事例を踏まえた考察」(財務省、2019年)など。

