<生命科学部は2008年4月に開設。4年生の所属は、前身の工学部生命機能学科>
2009.10.12
サイエンスは奥深く、楽しい
川岸教授研究室では、環境の変化に対する細胞の応答やその情報伝達の動きの解明を目指して日々研究に取り組んでいます。用いているのは“大腸菌”などのバクテリア。特に大腸菌は、約2-5 μm(マイクロメートル)=約0.002-0.005 mmと電子顕微鏡を使ってしか見えませんが、分子生物学の黎明期以来、精力的に研究されていて、地球上でもっとも詳しく研究されている生物となっています。細胞の情報伝達という面でも、細胞外からの刺激を感知する受容体や、細胞内の情報伝達・処理を司るタンパク質などが判明しており、世界中で幅広く研究されています。川岸研究室では特に、環境要因感知のセンサー分子群の構造や情報識別の仕組み、細胞内での情報伝達やその情報に応答する仕組みなどに関する諸研究を進めています。
「生物がどうやって生きているのか、その奥深い原理を探っているわけですが、学生には『サイエンスを楽しんでほしい』と常々言っています」と川岸教授。その一方で「研究は遊びではありません。いわば、人類の知識を地道に積み上げていく作業。その厳しさも同時に学んでほしい」と強調します。
学生たちは、個々のテーマで研究に取り組んでいます。なかには4年生にして、アメリカの大学の研究室と同じテーマで競争しながら研究を進めている学生もいます。飯島恵理さん(4年)のテーマはニッケル(Ni2+)に対する大腸菌の応答機構。ニッケルに対しては従来、大腸菌のセンサー分子がそれを感知する際に、仲介する物質があると考えられていましたが、「疑問を持って研究を進めたところ、その仲介物質のない菌でもニッケルを避ける応答が認められました」と飯島さん。直接的にニッケルを感知するセンサー分子を特定している点で、飯島さんの研究は一歩リードしていますが、「親身にアドバイスしてくださる先生や、意識の高い仲間とのディスカッションを生かして、さらに追求していきたい」と意欲満々です。
-
 電子顕微鏡で大腸菌を観察
電子顕微鏡で大腸菌を観察 -
 研究室での熱のこもった討議
研究室での熱のこもった討議
意欲を培うカリキュラムと自主性の尊重
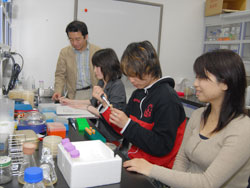
生物の奥深い原理を追求します
生命機能学科では2年生から研究室に所属する特徴的なカリキュラムで、学生の専門性と能力を高めています。
2年次は実験や英語の専門論文講読などを行いながら徐々に研究室や、専門研究に慣れていきます。
現在、3年生の多くは、GFP(緑色蛍光タンパク質=2008年ノーベル化学賞を受賞された下村脩博士が発見されたもの)を標識として用いて大腸菌の応答や情報伝達の仕組みの解明に取り組んでいます。山本健太郎さん(3年)は「多剤排出ポンプに着目した研究を進めています。最初思っていた以上に、充実した専門性の高い研究に携わっています」と目を輝かせます。一方、「1年次から実験・演習の授業もあり、高いモチベーションを維持しています。特に研究室では取り組んでいるテーマも面白いし、自由にやれるのが特徴です」と中村由樹さん(3年)も話します。
「やる気のある学生が多いだけに、求める水準も高くなります。」と川岸教授。研究室は学部2年生?院生、ポストドクターなどを含めて41人の大所帯。昨年竣工したばかりの東館の研究室は諸設備が完備されていますが、効率的に研究を進めるため、始終、研究室に詰めているのではなく、時にはフレキシブルに集中的に実験を行うなど、学生の自主的な判断を重んじています。
「学生には『結果を大事にし、実験で得たデータを穴のあくほど見つめ意味を考えなさい』と強く教えています」と川岸教授。それは失敗した時こそ重要です。「特に、正しい手順で行っても(思い描いた)データが出ないケースは、場合によっては新たな発見につながるチャンス。よく考えて、次の実験をデザインすることが必要。その意味でも実験ノートは研究室の共有財産。研究室の者なら誰でも見られるように、きちんとデータを記すことを学生に求めています」と川岸教授は話します。

