50号 2023年3月
沖縄文化研究所創立五〇周年 歴代所長寄稿文
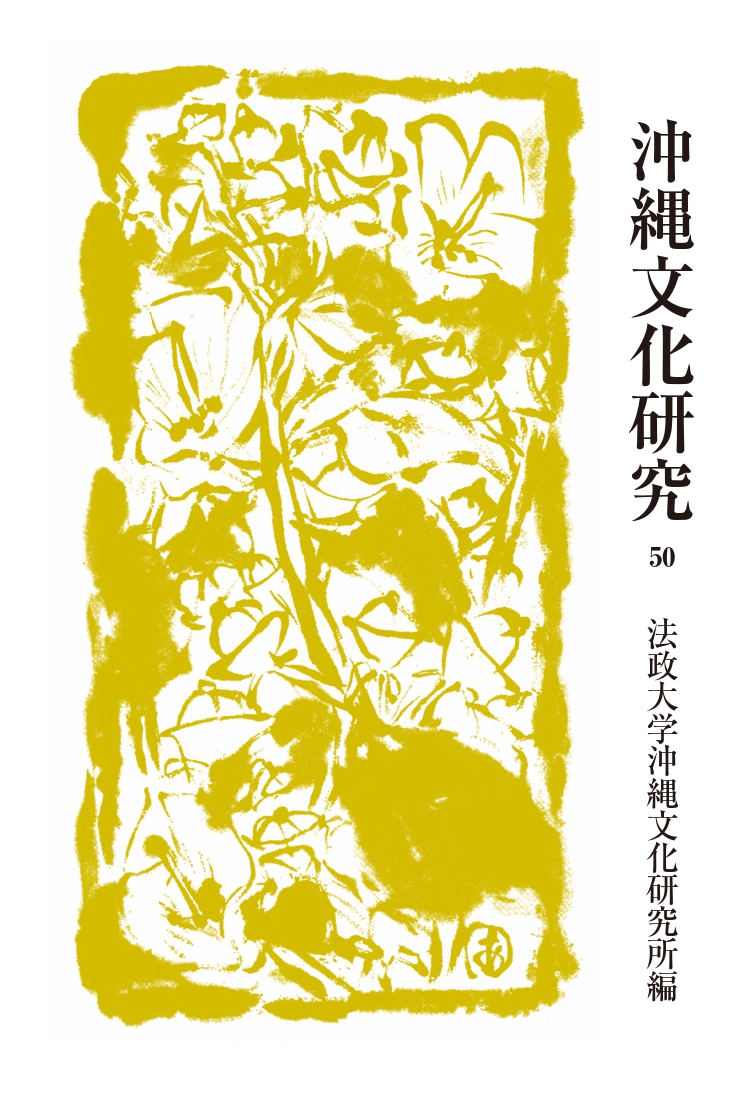
- 中野好夫さんの思いを引き継いで — まずは知ることから — 屋嘉宗彦
- 所長を二度、経験して 中俣均
論文
- 琉球文学の表現、唱えられる神話 —『久米仲里間切旧記』を資料として— 島村幸一
- 「ザー」の発掘調査にみる宮古島狩俣集落と祭祀の展開 石井龍太
- 近世琉球の「掠入」と生子証文の機能 伊集守道
- 寛文期前半の琉球・薩摩間における借銀交渉 —「唐商売方式」の成立過程— 伊藤陽寿
- 返還後の沖縄で自衛隊はなぜ受け入れられたか — 一九七二~一九七五 — 小口晃平
- 『おもろさうし』における神女の招請と対面 — 第一二と第七のオモロの検討から — 澤井真代
- 地租改正以前の奄美群島喜界島における村別生産活動の地域格差と寄高 島﨑達也
- 明清交替と琉球暦学の変容 — 楚南家旧蔵『廸吉全書』を中心に — 徐仕佳
- 蔡温による修史と第二尚氏の系図・廟制 前村佳幸
研究ノート
- ニコライ・ネフスキー旧蔵『おもろさうし』について — 天理図書館蔵『おもろさうし』巻十、解説と校異・翻刻 — 末次智
49号 2022年3月
論文
- 未完の地図―森崎和江と沖縄闘争の時代― 大畑凜
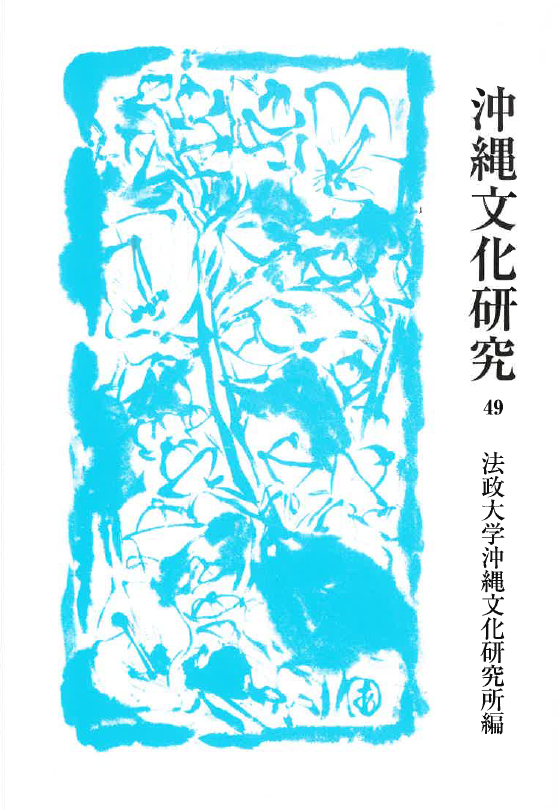
- 近代沖縄における校長の組織化過程―校長会の運営実態を分析視点として 藤澤健一
- 琉球処分をめぐる李鴻章の外交基軸―琉球存続と分島改約案 山城智史
- 弔いの場をひらく―沖縄戦体験者の家族のナラティヴを通して― 山本真知子
研究ノート
- 奄美群島喜界島における明治初期の村別人口と家畜―「喜界島各村地理表」の検証を目的として 島﨑達也
- 長期占領下沖縄の保健医療システム―保健所を中心に― 杉山章子
48号 2021年3月
論文
- 琉球の御拝ツヅ(ミハイツヅ) 島村幸一
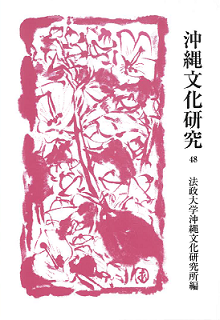
- 琉球王国における石碑作成に関する研究 矢野美沙子
- 19世紀沖縄の葬墓制とその変容―沖縄本島北部地域の事例を中心に― 加藤正春
- 琉薩間航路を往環する大型馬艦船の運用について 三枝大悟
- 山之口獏の詩篇における故郷の名称の変容 伊野波優美
研究ノート
- 祭祀の変容と継承問題―伊平屋島字田名のウンジャミとシヌグを事例に― カーズ・バーバラ
47号 2020年3月
論文
- 宮古島の士族「忠導氏仲宗根家」の家譜叙述 ―「八重山征伐」をめぐる悲劇譚と「征服」譚― 島村幸一
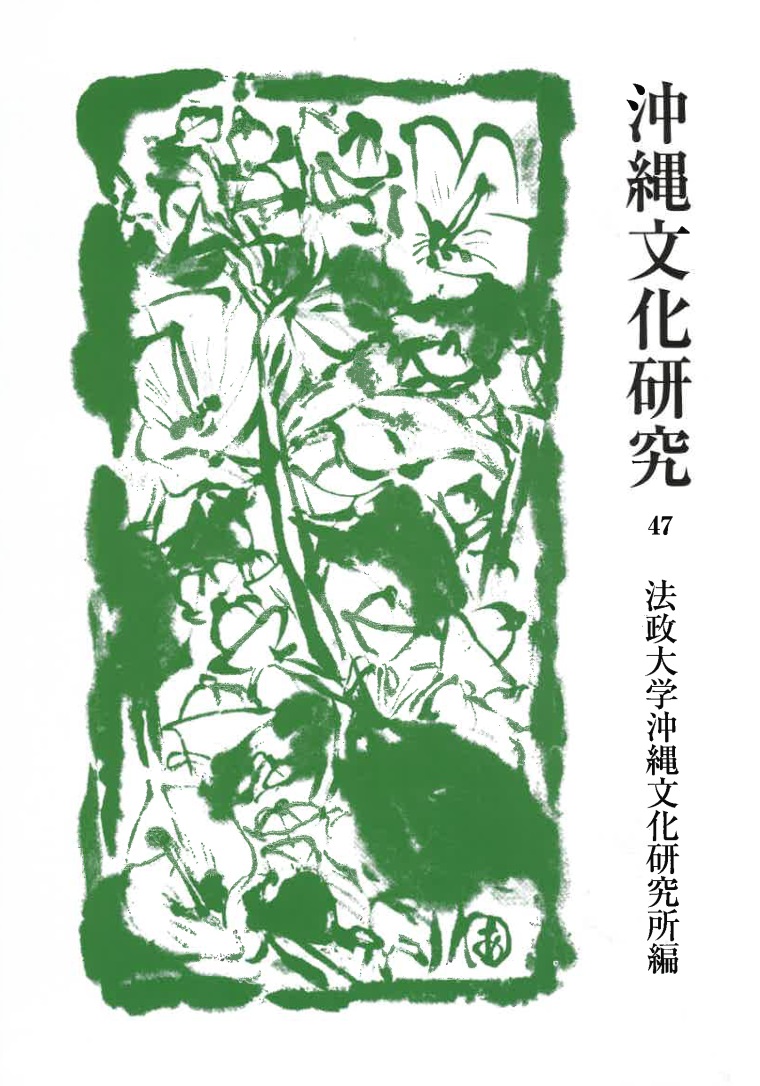
- 1960年代の沖縄観光について 桜澤誠
- 新資料から読み直す宮古島でのドイツ商船漂着(一八七三年)の経緯―イギリス船カーリュー号の関与と乗組員の数を中心として― 辻朋季
- 琉球王朝末期の廟議-寝廟と太廟の神主配置 前村佳幸
- 「シマ宇宙」への通路 ―宮古・南洋・八重山― 澤井真代
- メディアを往復する『風音』――映画化、作者、コンテクスト 藤城孝輔
研究ノート
- 廃琉置県処分後の沖縄統治と風説 ―「久米島出張復命書」を中心に― 前田勇樹
- 「軍政」から「民政」へ 米国統治移行期における沖縄の保健医療システム 杉山章子
新崎盛暉先生追悼特集
略年譜
主要著作
追悼文
- 沖縄で生きた父と私 新崎盛吾
- 共同研究「ミクロネシアと沖縄」をご一緒して 今泉裕美子
- 戦後沖縄にしか生まれ得なかった人間像 梅田正己
- ことばといき方と 親川裕子
- 新崎盛暉さんと宮里政玄先生 我部政明
- 新崎盛暉さんの周辺にいて 我部政男
- 『けーし風』の集いをめぐって想起すること 鳥山淳
- 沖縄大学中興の祖 仲地博
- 新崎盛暉さんとの47年 西泉
書評論文
- 新崎盛暉『私の沖縄現代史:米軍支配時代を日本(ヤマト)で生きて』岩波書店2017 阿部小涼
研究ノート
- 新崎盛暉の仕事から学ぶこと 屋嘉宗彦
- 沖縄資料センターから法政大学沖縄文化研究所へ 大里知子
追悼論文
- 「吹きかえし」の風を待つ少年—東峰夫「オキナワの少年」と一九五〇年代の沖縄— 若林千代
- 繰り返されるコモンズの収奪にどう抗うか──新崎盛暉と一九七〇〜八〇年代 上原こずえ
- 米国は1965年の宮古農民「暴動」をどう見たか 古波蔵契
46号 2019年3月
論文
- 勢理客文吉=イスマイル・B・セリキャクの歴程:沖縄・硫黄島・インドネシア 後藤乾一
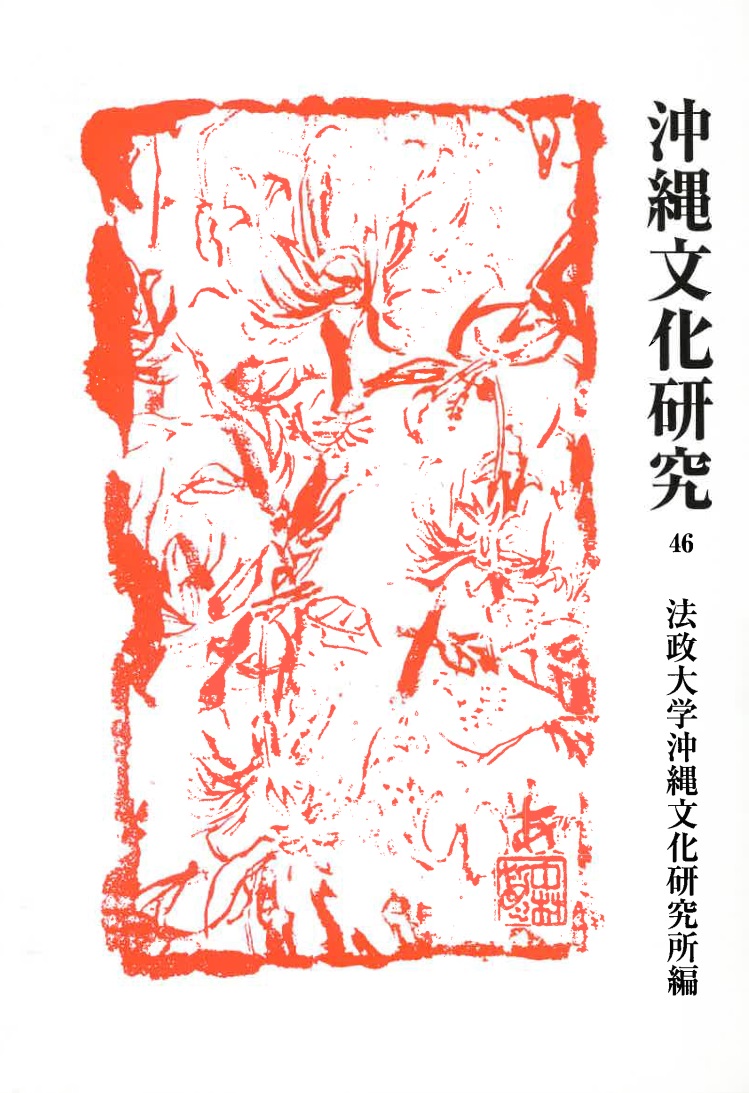
- 種子どりとにぎりめし:シラを舞台とした季節儀礼の比較研究から 藤井紘司
- 宣教医ベッテルハイムの琉球王国宣教とそのイギリス帝国宣教史上の意義 渡邊公夫
- 近代沖縄の教育会における役職者の変容過程:一八八〇年代から一九四〇年代はじめまでの人的構成 藤澤健一
- 大城立裕の文学形成と『琉大文学』の作用:一九五〇年代の〈沖縄〉文学をめぐって 柳井貴士
研究ノート
- 沖縄と済州島における伝統住居の空間構成の比較 朴賛弼
報告
- 宮古島市池間島の祭祀と漁業:足跡と再生に向けて 加藤久子
45号 2018年3月
論文
- 女立ちの成立 : 御冠船踊りの近代化と琉球舞踊 板谷徹
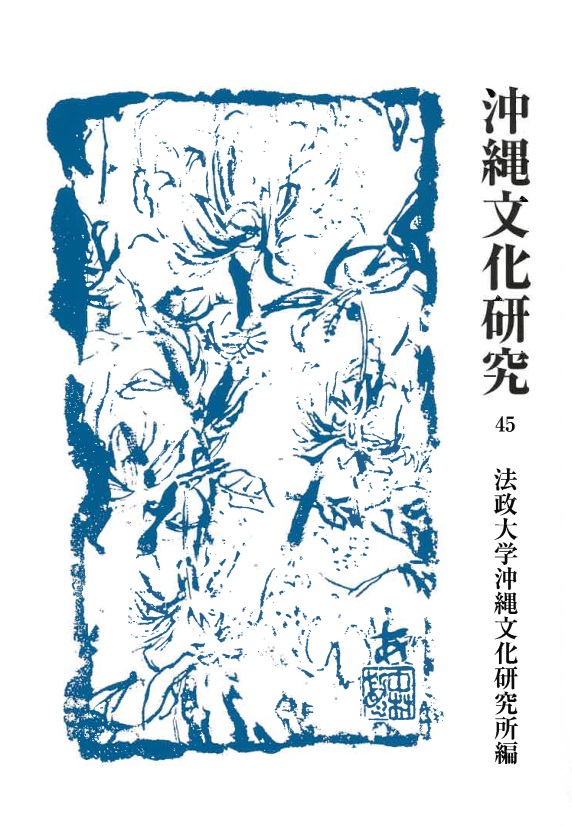
- 「沖縄文学」の特異性と可能性 大城貞俊
- 琉球王府の雨乞い儀礼 : 尚家文書「雨乞日記」「雨乞御代参日記」と雨乞いのオモロにふれて 島村幸一
- 海兵隊協力映画、米日琉合作映画、宣伝映画としての『戦場よ永遠に』(一九六〇年) 名嘉山リサ
- 一九世紀中葉の琉球における宣教様相とキリシタン禁制 : フランス人宣教師を中心に 下岡絵里奈
- 近世琉球における才府就任 : 旅役と地頭所分配の関係をめぐって 山田浩世
- 一八七〇年代前半の琉球(藩)における官公調査 : 鹿児島県管轄期と外務省管轄期を中心に 前田勇樹
- 占領期沖縄における土地接収と生活補償をめぐる折衝過程 : 伊江島の陳情者の座り込みまで 岡本直美
- 米施政権下における北部訓練場の軍事的土地利用はいかになされたか 森啓輔
- 近代沖縄における学務担当者の変容過程 : 一九〇〇年前後から一九四〇年代はじめまでの人的構成 藤澤健一
- 占領初期沖縄群島における六・三・三制の導入と教科書事情 萩原真美
- 第二次世界大戦後における沖縄からのボリビア移住に関する一考察 : 読谷村の集団移住を中心に 中山寛子
- 明治期沖縄県における「報道」から見る空手の諸相 : 『琉球新報』の分析を中心に 阿部暁之
研究ノート
- 占領初期沖縄の保健医療システム : 群島別の形成過程 杉山章子
44号 2017年3月
論文
- 琉球「科試」の実施状況について 水上雅晴
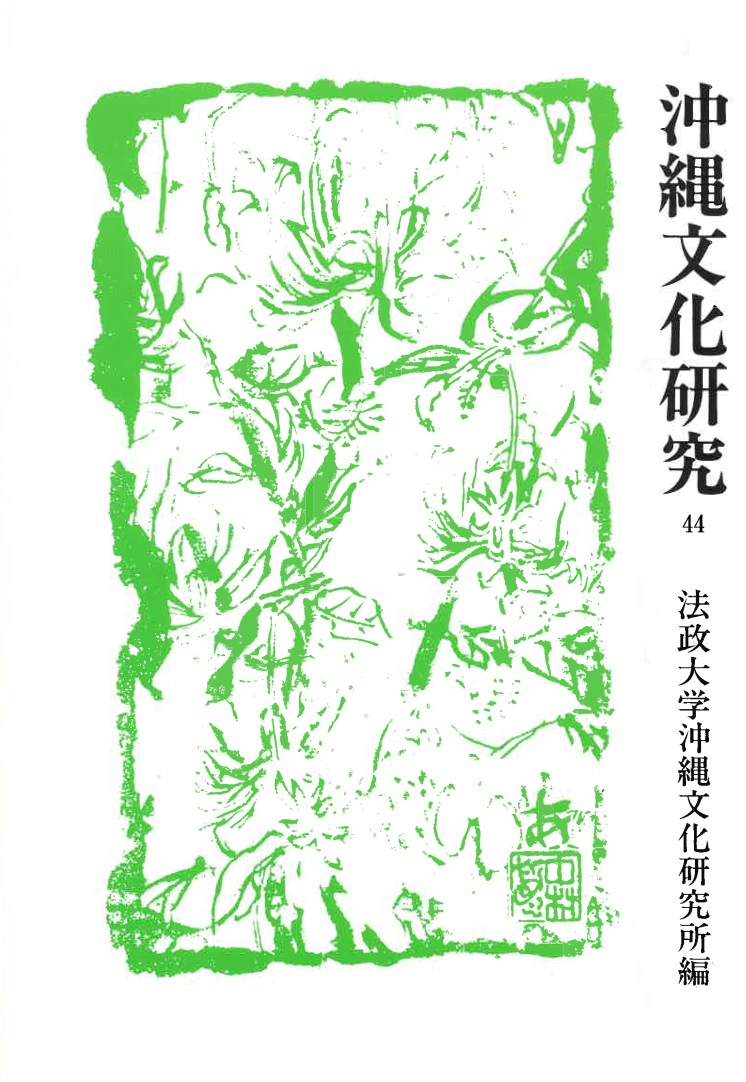
- 方言札の広がりととまどい―「普通語ノ励行方法答申書」(一九一五年)を中心に― 近藤健一郎
- 沖縄占領と労働政策―国際自由労連の介入と米国民政府労働政策の転換 古波藏契
- 沖縄戦をめぐる内部葛藤の物語―大城立裕「棒兵隊」論 柳井貴士
研究ノート
- 後水尾上皇・明正天皇の前で奏楽した琉球人 木土博成
- アルゼンチンにおける沖縄移民の救済活動と芸能 月野楓子
- 複数のオキナワ・アイデンティティ―沖縄県南大東島の事例 進尚子
43号 2016年3月
論文
- 奄美における沖縄返還運動 ―沖縄返還運動の歴史経験が奄美にもたらしたもの― 小野百合子
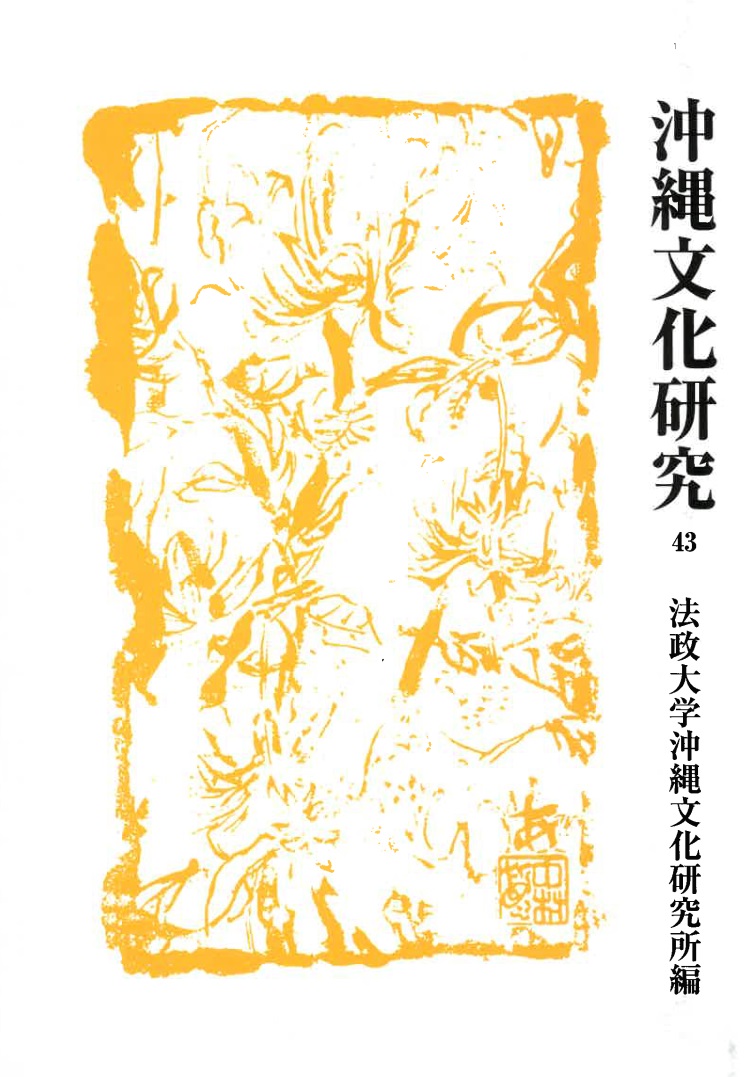
- 又吉栄喜「ジョージが射殺した猪」論―占領時空間の暴力をめぐって― 柳井貴士
- 謝花昇と沖縄倶楽部の結成 伊佐眞一
- 近世八重山への王府布達文書「規模帳」「公事帳」の成立過程 得能壽美
- 泰請封問題と琉仏約条 ―一八五五年・一八五六年におけるフランス人逗留問題から― 伊藤陽寿
- 廃琉置県直後の沖縄県庁運営の実相 ―首里王府役人の採用をめぐる問題を中心に― 前田勇樹
- 葬儀の作り物とその考察 ―沖縄県八重山地方与那国島の葬儀の事例から― 古谷野洋子
研究ノート
- 沖縄県の児童は卒業まで小学校に通い続けたのか ―一九二〇年代半ばから四〇年代半ばまでの『文部省年報』をもとに 田中萌葵
42号 2015年3月(外間守善先生 山本弘文先生 武者英二先生 比嘉実先生 追悼記念特集号)
はじめに
年譜・主要著作
追悼文
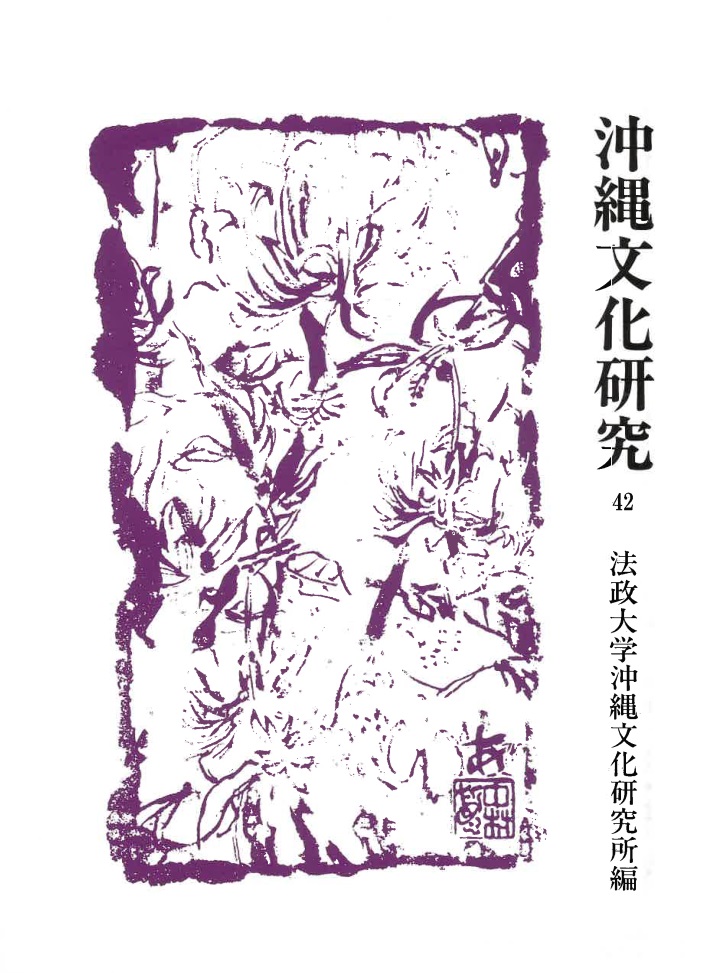
- 山本弘文先生のご逝去を悼む 安江 孝司
- 武者英二先生を偲ぶ―建築そして沖縄の民家と集落空間を求めて― 永瀬 克己
- 比嘉実先生を偲ぶ 島村幸一
論文
- この半世紀の琉球文学研究、そしてこれからの研究 波照間永吉
- おもろさうしの叙事性 竹内重雄
- オモロの囃子詞 松永明
- 『おもろさうし』にみる神話、伝承、他界観 ―国王の行幸と「創世オモロ」をめぐって― 小山和行
- 『おもろさうし』の助詞ガの表記再考 間宮厚司
- 外間守善、宮古歌謡体系化の軌跡 新里幸昭
- 宮古島狩俣の「ニーラアーグ」をめぐって 上原孝三
- 越州窯青磁―キカイジマ・『源氏物語』・唐物― 福寛美
- 琉球から見た『椿説弓張月』 島村幸一
- 新しい美意識の登場―明治琉歌の見出したもの― 仲程昌徳
- 尚寧王の駿府・江戸往還について―『喜安日記』の研究(一)― 梅木哲人
- フクギについて(覚書) 田名真之
- 琉球近世の経済構造―山本弘文先生の研究に触れつつ― 来間泰男
- 在米時代の宮城與徳とその周辺群像―孤高の移民画家の肖像― 比屋根照夫
- 沖縄戦争時期のスパイ(防諜・間諜)論議と軍機保護法 我部政男
- 沖縄戦で失われた集落の再建と米国の統治法規による占領政策 加藤久子
- 沖縄における記録活用の可能性 齊藤郁子
- 沖縄の発展と展望―沖縄の伝統的住まいを継承するエコハウスを目指して― 朴賛弼
- ウチナー・イーチリー・イカットロード―回顧断想― 安江孝司
- 山本弘文先生の沖縄研究をたずねて 東喜望
41号 2015年3月
論文
- 徳之島における三平所と手々村神役の継承システム―琉球と薩摩藩の影響を受けた文書とシマの運営を含め― 弓削政己
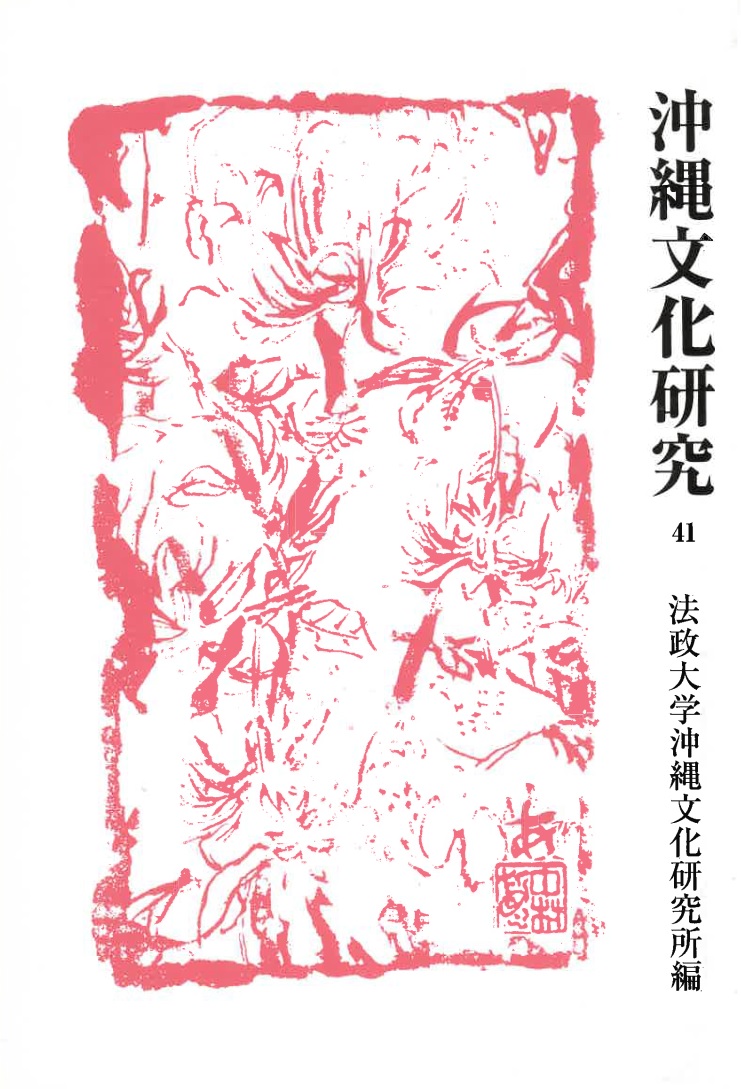
- 琉球中央士族の漢籍学習について―楚南家本を中心とする初歩的考察― 水上雅晴
- 琉球使節の江戸参府から見る幕末期日本外交の変化―近世から近代へ― ティネッロ・マルコ
- 明治期の琉球における真宗法難事件に関する一考察―善教寺資料を中心に― 川邉雄大
- 水産技術者宮城新昌と故郷沖縄の「振興」「復興」 山本ちひろ
- 日本復帰前後からの島ぐるみの論理と現実主義の諸相―即時復帰反対論と沖縄イニシアティブ論との対比的検討から― 秋山道宏
- 目取真俊『魚群記』論―台湾人女工をめぐる政治・経済・欲望― 佐久本佳奈
- 古川成美『沖縄の最後』におけるテクストの変遷と戦場への眼差し―初出版の問題点と改訂版の差異をめぐって― 柳井貴士

