「法政の研究ブランド」シリーズ
法政大学では、これからの社会・世界のフロントランナーたる、魅力的で刺激的な研究が日々生み出されています。
本シリーズは、そんな法政ブランドの研究ストーリーを、記事や動画でお伝えしていきます。
イタリアで「テリトーリオ」「地理的表示(GI)」というテーマに出合う

2012年にイタリアに渡り、ヴェネツィア大学で2年間客員教授を務めたのですが、そこで現在取り組んでいる「テリトーリオ」「地理的表示(GI)」「地域活性化」という研究テーマに出合いました。それ以前は消費行動論を研究していたのですが、イタリアの各地で調査し、都市と農業がとにかく近く、地域の人たちが享受している豊かな社会を目の当たりにし、これらのテーマに関心を持つようになりました。
「テリトーリオ」という言葉は聞きなれないかと思いますが、『イタリアのテリトーリオ戦略』『南イタリアの食とテリトーリオ』という書籍を一緒に出版した、法政大学江戸東京研究センター特任教授の陣内秀信先生の定義によれば、「社会経済的、文化的なアイデンティティを共有する空間の広がりとしての地域あるいは領域」を「テリトーリオ」と呼びます。イタリアには農作物を加工し、さらに販売して消費する都市(旧市街・居住エリア)とそれを取り囲むように田園(農村)が広がる小さな村が点在しています。
もう一つのテーマである「地理的表示(GI)」は、産品の味、形状、品質などの特性が、それらが生産される産地ならではの特性によりもたらされるという結び付きを証明し、社会的評価があるときに認証される名称のことです。日本の農産物、食品でいうと「夕張メロン」や「神戸ビーフ」などが該当します(2025年1月現在154産品)。日本でも親しまれているチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」はエミリア・ロマーニャ州とロンバルディア州の五つの地域で決められた工程で生産されたものだけが、その名称を使えます。私の研究の目的の一つは、GIとそれを保護する仕組みである「地理的表示(GI)保護制度」により、農村を振興することです。
1919年にワインの模倣品排除を目的として、フランスでGIに関する法律が制定されました。生産地と消費地が同じであれば、誰が生産しているのかを消費者が知っているため、GIは要りません。ところが都市化とグローバル化によって、生産地と消費地の時間的・物理的距離が遠くなればなるほど、誰がどこでどのように生産したのかわからないため、模倣品が出回ってきます。そのため、正規品と模倣品を区別するために、GIが生まれました。EUの中でもイタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、ギリシャでGI産品が多いのですが、共通しているのは、地中海沿岸諸国で、地形が多様で食に対する意識、郷土料理への愛着が強く、伝統を守る国々ということです。
-

日本の地理的表示で保護されている「神戸ビーフ」の枝肉。バイヤーがセリ前に状態を確認した後、競売にかけられる(2017年)
-

EUの地理的表示制度により保護されているチーズ「グラナ・パダーノ」の熟成庫にて、時間をかけて熟成される伝統的なハードチーズ(2014年3月)
社会経済的なつながりを超え文化的なアイデンティティを共有するテリトーリオ

私はテリトーリオについて、農産物と食品から調査していましたが、陣内先生は、都市の中でテリトーリオを研究されていました。私が農村から都市、陣内先生が都市から農村という形でそれぞれが研究の領域を広げ、「都市とそれを取り巻く田園のまとまり」という概念へと繋がったのです。例えば、食をキーワードにして考えると、農村で生産される農産物は、そこでそれらが消費までされるわけではなく、加工する場所や流通させる場所、さらに消費する場所があり、このまとまりがテリトーリオなのです。この概念はイタリアに限らず、近年EUで広く振興されています。一番の理由として、昨今の環境破壊による異常気象への危機感があります。食料自給の持続可能性を永らえさせるには、今のような資本主義的経済システムは限界にきており、地域循環型農業によって何とかこれを変えなければという強い意識があります。
日本にもテリトーリオ意識は存在していましたが、廃藩置県や農村の都市化によって同じアイデンティティを持つ人たちが分断されてしまったため、薄れてしまいました。テリトーリオは、単に農作物の生産から消費の単位にとどまらず、同じアイデンティティを持った人たちの暮らし全体のまとまりであり、社会経済的な結びつきを超えた、文化的なアイデンティティを共有する地域を意味します。これにはまず、地形が産業をつくるといえます。例えば水路があることでモノを運べます。また水は動力としても使われてきました。お酒をつくるためにはきれいな水も必要です。だから水は非常に重要な共有財で、枯渇させないようにみんなで守りつつ使っているのです。コモンズの精神と地域に固有の共有財、これは在来品種もあるし、水や土壌も含まれますが、それら自然要件と、それを活かす作り手、職人といった人的要件が合わさることで、テリトーリオの個性が生まれます。
岩手で行われる「日本型テリトーリオ・モデル」の構築
日本における研究も始動して、2024年「農村と都市との豊かな結びつきを育む『いわて畜産テリトーリオ』創造拠点」プロジェクトが、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が公募する令和6年度「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)【地域共創分野・育成型】」に採択されました。これまで畜産における課題は、技術や医療、生産効率といった側面が注目されてきましたが、プロジェクトリーダーを務める岩手大学農学部の澤井健教授がテリトーリオの概念に共感くださり、私もメンバーの一員として、食育やショートサプライチェーン、地域循環型農業を通じた地域のアイデンティティ形成といった側面から、畜産を通じた豊かな社会の創造に向けて取り組んでいくことになりました。①循環型飼料生産流通システムの構築、②多様な経営形態に適応可能な家畜飼養システムの構築、③先端通信技術による次世代獣医療体制の構築、④地域資源の活用による共創型地域圏の構築という四つの課題について、私は副プロジェクトリーダーとして、テリトーリオで地域の全てのステークホルダーを結び付けていきます。本プロジェクトは、テリトーリオの研究にとどまらず、社会実装化することを目指した、岩手県とその市町村が参画する行政横断型のプロジェクトで、これがうまくいけば日本の各地域に適用できるモデルを作ることができると期待しています。
日本においてテリトーリオの形成を成功させるためには、住民の皆さんが積極的に参加することが不可欠です。これまでの話から、テリトーリオとは、地形や建造物、在来品種の動植物など、可視化されやすく、そこに存在するものだと認識されるかもしれません。しかし私は、人々の活動とそれが生むコミュニティ形成が大切だと考えます。地域の歴史を再発見し、活用する活動を行うなかで、テリトーリオの価値に皆が気付いていく。そのプロセスこそが、日本型テリトーリオのモデルです。これまで農村のコミュニティは地縁がベースでしたが、これからはオープン・アクセスで誰でも参加でき、構成するメンバーも多様である必要があります。新しいステークホルダーとネットワークを作ることが、日本でもテリトーリオを形成していく条件です。
最後に日本におけるテリトーリオの可能性についても触れておきます。今日本では酪農が危機的な状況に瀕しています。その背景の一つは高齢化が進んで、農業従事者が激減していること。ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、肥料と飼料が高騰したことも大きな打撃となっています。牛乳は学校給食のある平日や学期中は一定の量が消費されますが、それ以外は飲用が減ってしまうなど、需給の調整が難しいという面もあります。日本ではコメの消費が激減して、耕作放棄地が増えていますが、牛の餌となる飼料米を、牛の堆肥を使って生産すれば、海外の諸事情の影響を受けずに、テリトーリオの中で循環型の経済システムを実現できる可能性があります。
こうした研究の成果を教育に還元することも重要です。ゼミでは一次産業による地域振興をテーマにしていますが、一例として、キャンパスで販売されている「ほうせい茶」の製品開発とプロモーション活動にゼミ生が携わっています。ここには「テリトーリオ」「農産物マーケティング」「地域活性化」といった要素が活かされています。
-
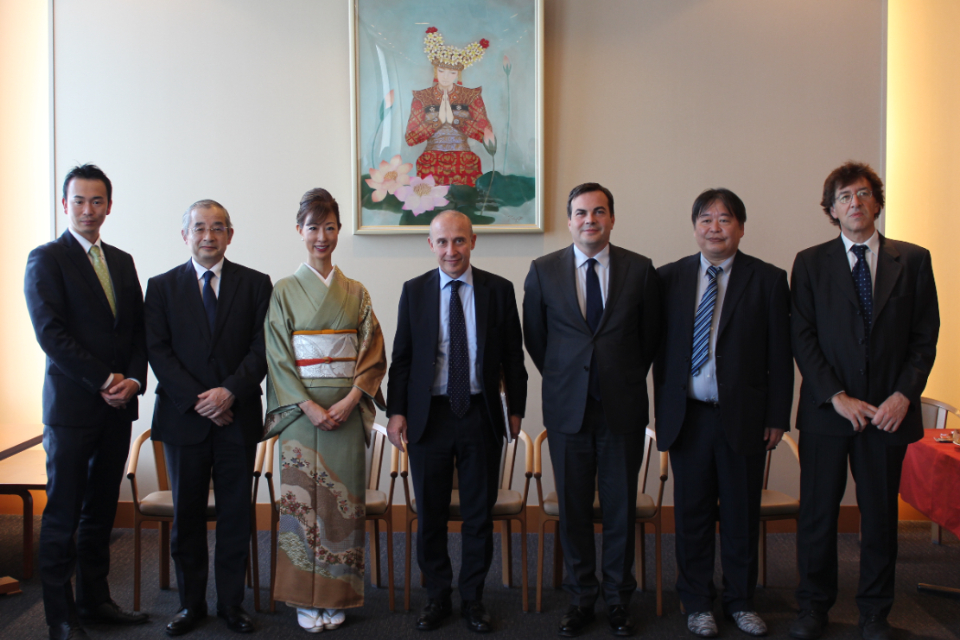
法政大学で開催した国際シンポジウム「地理的表示制度と経済連携協定」の登壇者(左から、西尾の抹茶生産者、法政大学尾川浩一常務理事、木村純子教授、駐日イタリア大使、イタリア外務省事務次官、農林水産省審議官、フィレンツェ大学教授)(2017年11月)
-

木村ゼミでのフィールドワークによる「GIの三島馬鈴薯」収穫の様子(2022年6月)
-

木村ゼミでプロデュースした「ほうせい茶」
-

「ほうせい茶」Tシャツを着たゼミ生との集合写真(2017年5月)
経営学部市場経営学科 木村 純子 教授
神戸女学院大学文学部英文学科卒業、ニューヨーク州立大学大学院コミュニケーション研究科修了(MA)、神戸大学大学院博士前期課程および後期課程修了、博士(商学)。研究分野は地理的表示(GI)、テリトーリオ、地域活性化。2005年法政大学経営学部助教授、同准教授を経て2010年より現職。農林水産省地理的表示に関わる検討会議学識経験者、財務省の国税審議会委員他。主な著書に『イタリアのテリトーリオ戦略―甦る都市と農村の交流―』(白桃書房)、『持続可能な酪農―SDGsへの貢献―』(中央法規)、『南イタリアの食とテリトーリオ―農業が社会を変える―』(白桃書房)など。

