こんにちは!経営学部広報委員会の櫻井史華、沖嶋駿也、五島玲奈です!
皆さんは、経営学部学術ゼミナール委員会という組織をご存知でしょうか?経営学部学術ゼミナール委員会とは、その名前の通り、経営学部生へのゼミに関する情報提供を行う組織で、今年度も発行された「ゼミシラバス」の編集を担っています。また、これに加え、新入生向けの交流会や履修相談、さらに就活セミナーの企画など、様々な面から経営学部生を支援する団体です。
今回は、前年度の「ゼミシラバス」の編集長で、現在は同委員会委員長を務める西山美帆(にしやま・みほ)さんに、委員会の活動内容についてインタビューをさせていただきました。また、2025年度の「ゼミシラバス」編集長の齋藤キララ(さいとう・きらら)さんに、書面にてインタビューに答えていただきました。ぜひご覧ください!
◎西山美帆さんインタビュー(対面)
1. 自己紹介をお願いします。
西山美帆と申します。経営学部経営学科3年です。今年度は学術ゼミナール委員会の委員長を務めています。前年度は、新しい取り組みであった「ゼミシラバス」の編集長を務めていました。
2. 「ゼミシラバス」を作ろうと思ったきっかけ、こだわった点、また難しかったことはありますか?
学生の皆さんが意外と分かっていない経営学部の演習授業、通称「ゼミ」について、学生ならではの視点で分かりやすく情報発信をしていこうと思ったのがきっかけです。ゼミについて詳しく分からないという声があったり、選んだゼミが自分に合わずやめてしまった友人がいるなど、こういった現状に課題意識を持ち始めたことも理由の一つです。
過去、経営学部では“Intoroduction to Seminar”という、学部が公式に作成するゼミについての情報誌がありましたが、私たち学術ゼミ委員会はゼミの詳しい情報などをより深掘りし、新たな「ゼミシラバス」を作ることができました。「ゼミシラバス」は、ゼミに興味を持った学生や、実際に入ろうとしている学生に一読してほしいものになっています。自分がゼミ選考の時に経験した「ゼミについてもっと知りたい!」という気持ちや、先ほどの例のようなミスマッチを防ぐという思いから初年度は作ったので、この記事を読んでいる学生の皆さんにもぜひ読んでもらいたいです。
こだわった点は、実際に手にとってもらう人にただ単に情報を伝えるのではなく、その中に面白さを加えたことです。ちょっと攻めた内容や、キャッチーな内容を取り入れるなど、様々なレイアウトにも工夫を凝らしました。文字の羅列を避け、写真を入れる場所も特に定めず、パっと手に取ってもらった時に感覚で伝わるようにしたいと特に意識しました。
「ゼミシラバス」を作るうえで難しかったことは、初めての企画だったということもあり、各ゼミの情報提出が任意だったので、参加ゼミ数も直前まで決まらず、ページ数や要項がなかなか見通せなかったことです。また、計画がうまくいかずにスケジュール調整が難しく、テスト期間を作成に当ててしまったこともありました(笑)。また、説得力を持った資料作りやレイアウトを考えることにも苦労しました。参加が任意であることから、多くのゼミが賛同してくれそうなレイアウトや、説明資料作りを心がけました。そしてこちら側の自己満足にならないよう、経営学部生のためのものだということを伝えるよう意識しました。

3. 学術ゼミナール委員会に入ろうと思ったきっかけは何ですか?
実は、学術委員会は数年前にコロナの影響でメンバーがおらず、消滅の危機にありました。しかし、今年3月に卒業された先輩方が立て直し、新入生向けの履修相談を担う「時間割お助け隊」などの活動を通じて、主体的に自ら行動するという目標をかかげ、なんとか立ち直ることができました。
私が委員会に参加しようと思ったきっかけは、他の委員とは少し異なる経緯があります。私は、2年生の段階からこの委員会に加入しましたが、きっかけは、時間割お助け隊の活動を通じて、先輩の委員に履修について詳しく教えてもらったことにあります。自分が経営学部の新入生に対して、履修のアドバイスやサポートを提供できることに大きな魅力を感じました。
また、私が1年生の秋ごろに、ゼミに関する相談会や「ゼミお助け隊」に参加した経験も、影響を与えていると思います。当時はゼミについてほとんど知識がなく、何から初めて良いのかも分からない状態でしたが、担当の方々に大まかなゼミの仕組みや入り方について丁寧に教えていただきました。その経験を通じて、ゼミの重要性や、自分が何かしらのサポートを通じて他の学生の役に立てることに気づき、自然とこの委員会に関わりたいという気持ちが芽生えました。
こうした経験の積み重ねが、今の私の活動の原動力となっています。自分自身もゼミや履修について学び、他の学生のサポートができることにやりがいを感じており、その思いを忘れることなく活動していきたいと思っています。
4. 活動のなかで意識していることはありますか?
私が活動を進めるうえで、特に大切にしていることは、自主性と、組織の役割の明確化です。先代の委員長を務めていた先輩は、自主性を非常に重視されており、自由に動きながらも責任をもって組織を運営されていました。その姿勢に触発されて、私も自主性を信念としています。自分から積極的にアイディアを出し、行動し、必要に応じて周囲と連携しながら進めていくことが、組織の活性化や新しい取り組みの推進につながると考えています。
また、委員長としての役割においては、様々な活動や取り組みを行う中でも、組織全体の方向性や役割を俯瞰して確認することを意識しています。具体的には、日々の活動に追われながらも、時折立ち止まり、今の活動が経営学部のサポート役として適切に機能しているかどうかを振り返る時間を設けています。
将来的には、さらに外部との連携を強化していきたいと考えています。具体的には、キャリアセンターや経営学部の卒業生の方々と協力し、より広い視野で学生支援や活動の充実を図りたいと思っています。例えば、経営学部の学生を対象にしたビジネスコンテストの開催や、企業・他大学とのコラボレーション企画など、多様な取り組みを企画・実現していきたいです。

5. 学術ゼミナール委員会の活動の中で、やりがいを感じたエピソードを教えてください。
「ゼミシラバス」の作成活動の一環で、「ゼミセミナー」というものを行ったことがあります。そして実際に、私の話を聞いて、私のゼミに入ってくれた方がいたことが一番やりがいを感じた瞬間です。ゼミセミナーの中で、私自身のゼミへの入り方について紹介したのですが、実際にそれを聞いてゼミに入ってくれた学生がいて、学術委員会の活動や自分の声が届いていることを実感しました。また、チームで一つのことを達成することも良かったと思います。例えば、「ゼミシラバス」の作成活動は、「自由を生きる実践知大賞」にノミネートされましたが、こういったことを通じて交友関係を広げることができました。
また、委員会に入って変わったこととしては、今まで以上に自分自身の役割を自覚するようになったことです。今までは、個人レベルの活動が多く、他人に何かを働きかけるという力はありませんでした。しかし学術ゼミナール委員会に入って、委員長という立場に立つこととなり、多くの人に影響を与えられる力を持つことができました。
そのために必要なこととして、資料作りの重要性も理解することができました。「ゼミシラバス」の協力を呼びかける際も、伝えたいことを絞って伝えることを意識しました。自分自身が飽き性なので、出来る限り聞いている人が飽きないような発表を意識しました。
6. 最後に、経営学部生へメッセージをお願いいたします。
色々な学年の人がこの記事を読んでいると思います。そのうえで、皆さんも何か一つ頑張れることを見つけてほしいなと思います。その手助けのコンテンツとして、ぜひ「ゼミシラバス」を活用してください。

◎齋藤キララさんインタビュー(書面)
1. 自己紹介をお願いします。
はじめまして、齋藤キララと申します。経営学部市場経営学科2年で、今年度の「ゼミシラバス」の編集長を務めています。昨年度も「ゼミシラバス」のチームメンバーとして活動していました。
2. 今年の「ゼミシラバス」の意気込みはありますか?
今年度の「ゼミシラバス」は、とにかく「学生目線」で情報を掲載することを大事にして作りました。最後まで飽きずに読めるように、写真やデザインの配置を工夫したり、ゼミを真剣に探している人から、「ちょっと見てみようかな」というくらいの人まで、幅広く役立つ充実したコンテンツになるよう意識しました。そして、ゼミ同士を比較しやすいように情報を整理して、どこから読んでも必要な情報にすぐたどり着ける構成にしています。
冊子を作る過程では、メンバー同士で意見を出し合いながら、学生目線での見やすさや面白さを何度も確認しました。実際に冊子として完成し、配布も始まったので、これから多くの方がページをめくりながら、気になるゼミを見つけてくれるのを楽しみにしています。
3. 活動する中で難しかったことはありますか?
ゼミごとに提出された情報量や雰囲気が違ったので、それぞれの個性を活かしつつ、読みやすくなるようレイアウトや構成を工夫するのが一番大変でした。また、日程や選考情報など正確さが求められる部分は、ゼミ生だけでなく学部事務の方や委員会メンバーにも何度も確認を取り、間違いがないように進めました。さらに、メンバー同士で意見を交換しながら、どのページも学生が見やすく、情報が頭に入りやすいよう調整しました。
作業は大変でしたが、ページが形になっていく過程は楽しく、ゼミそれぞれの魅力を最大限伝えられたと感じたときは嬉しかったです。完成した冊子を手に取ったときは、ワクワクしながら学生の反応を想像していました。
4. こだわり/見てほしいポイントはありますか?
正直、特定のページよりも、全体の一体感を見てほしいです。今年度は委員会メンバーだけでなく、他の学生からも意見を聞き、どんな情報があると便利か、どうすれば読みやすいかを模索しました。その声を最大限活かして、昨年度から引き継いだトピックページはもちろん、今年度新たに追加したゼミ関連ページでも工夫をしました。ゼミプロフィールでは雰囲気が伝わるように写真やレイアウトを工夫し、ゼミ選考ノートや大学公開情報ではゼミ選考に重きを置き、少しでも悩みがちなポイントを減らせるようにしています。
また、定期的に意見交換会を開き、チームメンバー同士でページの仕上がりを確認しながら作ったので、細かい部分まで読みやすさにこだわることができました。冊子全体にわたってこうした工夫を詰め込んでいるので、ぜひページをめくりながら、情報の見やすさや楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。
以上、お二人のインタビューをお届けしました。
今年度の「ゼミシラバス」作成に際して、より磨かれた点や、新たな試みなどの努力がよくわかるインタビューになりました。「学生目線」を発揮した今年度の「ゼミシラバス」はきっと読みやすいものになっていると感じました。ありがとうございました。
学術ゼミナール委員会のインスタグラムのURLは次の通りです。様々な情報が発信されていますので、訪れてみてください。
https://www.instagram.com/hosei_gakujutsu?igsh=MTc5bm1kYm5xb2R0Mg==
また、「ゼミシラバス」は大内山校舎1階の、証明書自動発行機の前の机に置いてあります。在庫切れになってしまう前に、お早めにお取りください。
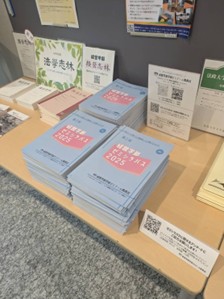
◎学生記者の感想
学術ゼミナールについて詳しく知ることができ、とても楽しいインタビューでした。また、ゼミについてまだ知らないことが多かったので、ゼミの選び方やゼミの活動内容などを深掘りしたことは、非常に勉強になりました。そして、大学生活の中で、何か頑張ることを見つけ努力することの大切さを改めて実感することができました。(櫻井史華)
学術ゼミナール委員会は、入学オリエンテーションで活動されていたことが私も印象に残っています。インタビューを通し、どのようなことを行っているのかを詳しく知ることができ、良い機会となりました。また、自主性を持って行動することの大切さを学ぶことができました。(沖嶋駿也)
学術ゼミナール委員会の活動や、「ゼミシラバス」作成の経緯について知ることができて、作成した側の思いが伝わってきました。今年度の「ゼミシラバス」を、私も大いに活用していきたいと思っています。(五島玲奈)
取材:櫻井史華(経営学部1年)、沖嶋駿也(同)、五島玲奈(同)

