2024年12月14日(土)に総長室が「学生が考える未来のキャンパス ~こんなキャンパスあったらいいな~」を開催し、24名の学生が参加しました。
①概要
本学は、永続的に教育・研究・社会貢献に取り組んでいかなければなりません。それを支えるのがキャンパスです。現在、総長室では将来的なキャンパスの施設整備構想である「キャンパスグランドデザイン」の策定に取り組んでいます。今回は、キャンパスの主役である学生に、将来、法政大学でどのような学びを実践したいか、またその実現のために、どのようなキャンパス(施設整備)が必要かについて考えていただき、キャンパスグランドデザインの策定を推進している総長室の西田室長に「こんなキャンパスあったらいいな」として提言してもらいました。
②参加学生団体
キャンパスの魅力を熟知し、それを発信しているオープンキャンパスの学生スタッフと、実践知を体現し、自由を生き抜く実践知大賞にノミネートされた学生に参加していただきました。参加団体は以下の通りです
- 市ケ谷オープンキャンパススタッフ
- デザイン工学部・社会空間情報研究室
- 多摩オープンキャンパスリーダーズ
- たまぼら佐野川プロジェクト
- GBC(ガラス箱オフィスアワーセンター)

参加した学生との集合写真
➂概要説明
冒頭、総長室の西田室長より、今回の企画概要について説明があり、その上で、現在に至るまでの各キャンパスの施設整備の経緯の説明がなされました。また、各建物の機能や役割分担を踏まえ、今後の施設整備を行う必要があると考えている旨の説明がなされました。

西田総長室長からの概要説明
④学生が考える「こんなキャンパスあったらいいな」
それぞれの学生団体が、将来、法政大学でどのような学びを実践したいか、またその実現のために、どのようなキャンパス(施設整備)が必要かについて考え、「こんなキャンパスあったらいいな」としてとりまとめ、下記の通り提言がなされました。
■市ケ谷オープンキャンパススタッフ
~「交流から得られる学び」と「個から得られる学び」が実現できるキャンパス~
・交流から得られる学びを促進するために新たな学生ホールの設置。
ホールには議論から生まれたアイデアを何処にでも書き込めるような机や壁の設置や大きなディスプレイ等を設置する。
・学生間の交流を促進させるため、富士見坂食堂にカフェの設置。
・個から得られる学びの実現にあたり、完全個室の自習室を設置し、じっくり考えることが必要な自習や就職活動の面接の練習が出来るようにする。
■デザイン工学部・社会空間情報研究室
~他学部との交流の促進~
・デザイン工学部がある市ケ谷田町校舎において、他学部との交流を促進するために、教養科目などの一部の科目については、他学部の学生と共に学べるような仕組みやそれを実現できる教室を整備する。
・市ケ谷田町校舎のカフェテリアを、より交流の場として機能できるよう整備する。
■多摩オープンキャンパススリーダーズ
~机上では学べない学びを提供するため、学部間、地域との交流が活発になるような施設整備~
・交流する場を増やすため、A棟エリアに集える場所を設け、そこでゼミやSIC等で考案・開発したものを発表出来たり、地域の方々が出展出来るような市場を設けたりして、学部間、地域交流を推進させる。
~キャンパス間の横のつながりを強くする~
・全キャンパスの空き教室を全学生が把握出来るようにすることで、空いている教室は交流の場や自習の場として提供することが出来るようになる。
■たまぼら佐野川プロジェクト
~バリアフリーに配慮した施設整備~
・多摩キャンパスの魅力は、高齢者や子供や障がい者などの多様な方々と交流出来ることである。そのため、多様な方々とキャンパス内で交流が出来るように、エレベーターやスロープを設置するなど、バリアフリーに配慮した施設整備をする。
~学部間連携が可能な施設整備~
・スポーツ健康学部などはキャンパスの中心部からは若干離れているため、新たなモビリティの導入や、学部間連携が可能なような施設整備をする。
・社会の課題解決を実践しているSICの場所をキャンパス内の目立つ場所に再配置することで、SICの存在をより広く認知させ、課題解決の実践の場としての多摩キャンパスを広くアピールする。
■GBC(ガラス箱オフィスアワーセンター)
~文理融合キャンパス~
・ERP(英語強化プログラム)などで市ケ谷の学生と交流する中で、理系学生と文系学生の人柄や学びに対する考え方の違いを実感し、学びの視野が広がった経験から、日頃から文系と理系の学生が共に学べるような文理融合のキャンパスを実現させる。
・山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムなどの有益な情報が、早い段階から知ることができる仕組みの構築。
-

グループでの議論の様子①
-

グループでの議論の様子②
-
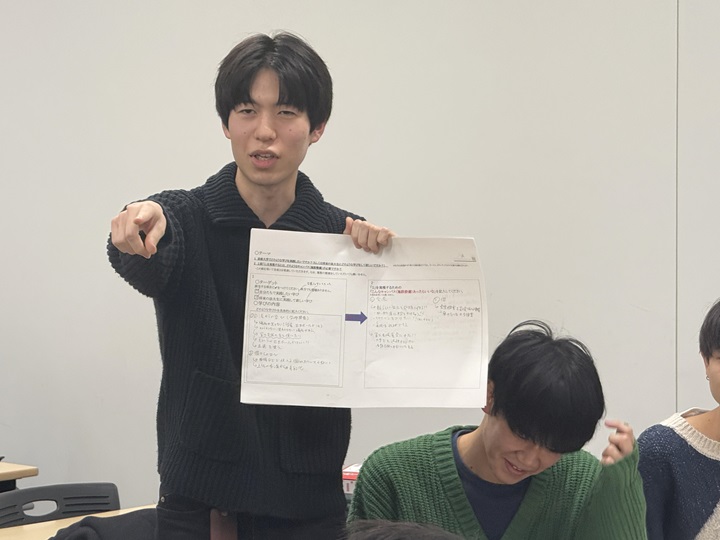
発表の様子
⑤まとめ
本日の企画を通して、キャンパスの主役である学生から様々な貴重な提言をいただくことができ、学生間の交流を促進するカフェテリアや学生ホールを設置することが本学の大きな強みになること、また、学部間、キャンパス間の交流が重要であることなどを改めて認識することができました。本日の提言を参考にしながら、今後の検討を進めていきたいと考えております。

